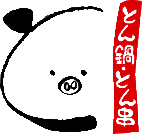鎌鼬と野槌と 第二話
「せんせい妖怪」
カマイタチは覚えている。その男の中にまた一匹奴らが産声をあげたその日のことを。
岡島至がいわゆる脱サラをはたし、勝手知りたる地元でそろばん塾を開いた理由は、実のところ本人にもよく分かっていなかった。昔から考え込むタイプの男ではあったが、自分のこととなると、ことのほか前も後ろも見えなくなってしまう。
おそらく一つには人にものを教えるという仕事はせちがらい営業のサラリーマン時代とは違い、クライアントから月謝をもらいながらも「ありがとうございます」と感謝の声をかけられる得点があったからというのが考えられる。そして一つにはサラリーマン時代によく上司から呼ばれたように「至、至らず」などと小馬鹿にするような呼び捨てではなしに、「岡島先生」と敬意を込めた呼称で呼ばれる空想に鼻をふくらませながらあかるい兆しを感じていたからに違いない。
開業したのがそろばん塾であった理由はそれが風采のあがらなかったこれまでの自分であれ、過去を振り返ってみた際、それが最も得意なことであったからであり、開業資金も机とそろばんさえあれば他に何もいらず安くはじめられたからである。この部分に気がついた際には岡島も膝を一つ叩いて自ら得心したものだった。
都落ちで戻ったにしろ、開業するのは勝手知りたる地元であったため、宣伝活動にもそれほど力を入れる必要はなかった。かつて同級生であった人たちの子供を預かる形で営業を開始することができたからである。特段目立った方ではなく、同窓会の日ですら卒業名簿を引っ張り出さねば誰も顔を思いだしてくれない岡島ではあったが、とにかくそろばんだけはやけに達者な男が一人いたという印象だけは皆の記憶にも少しは残っていたようだった。
そういった弱者としての立場は、ときとして隠れた功名心を巧みに和らげてくれる効果を及ぼしてくれる。営業行為として、こちらがわにとって有利に働くことがある。
これは営業マン時代に覚えた唯一有意義な心理現象だといえた。
岡島至は、授業の初日はさすがにそろばんを弾く手が震えたのを今でも覚えている。白板をさす右手の人差し指も震えていたし、数珠をはじく右手の親指も震えていた。
岡島がいつも深爪気味に爪を処理する癖があるのは、算盤をはじく際、爪が邪魔になるのを予防するためである。子供の頃から、これだけは得意だった。与えられた計算式を、ただひたすらに足したり引いたり割ったり、掛け合わせたり。
「そんなものは、女の事務員でもできるんだよ。だいいち、いまはパソコンが全部やってくれる」
あれは飲んでいる席でのことだった。サラリーマン時代に、岡島の上司は彼にそういった。
岡島は、それを思い出すたび、米神の辺りに血が行き場無く溜まるのを感じる。
だんじて、そんなことはない――。
気がつけば、岡島は教壇のうえに右腕を振り下ろしていた。
教鞭用の大きな算盤模型が砕け散り、数珠がちりちりと音を立てて子供達の足下へ散らばってゆく。
「失敬。ちょっと腕があたっただけだ。ナンでもないから計算を続けなさい」
右腕が言うことをきかなくなりだしたのは、一体何時の頃からだったか。
感情的になると、どうにも抑止がきかなくなる。
「どうした、計算を続けなさい」
気がつけば、唾を飲みながら生徒達が岡島の顔色を窺っていた。
岡島の号令に従うようにして、子供達はまた算盤をはじき始める。
この算盤教室が岡島に彼の求めていたほぼ全てをもたらしてくれた。
女房の公子ともこの算盤教室を通じて知り合った。こぶつきなのが玉に瑕ではあるものの、公子は付き合ってみるとつくづくいい女だった。一度食らいついたら飽きてもまだはなさない。子持ちの独身女がこうまで男に飢えるものだとは。先のことを考えるのは今は億劫だが、素人の女を知らない岡島にとっては、今まさにうってつけの女だった。
ただ、問題が一つ……。
「どうした、何をぼうっとしている。計算を続けなさい」
岡島は、まだ正式に縁組みを済ませていない義理の娘にそういった。
「ヨウカイだ」
「え。ナンだって?」
「みぎてにヨウカイがすんでいるんだ」
「……何を馬鹿なことを」
――。
夜、床の中で女房が言った。
「ねえ、あなた、ちょっと生徒たちへの体罰が過ぎるんじゃないのかしら。悪い噂がたっているわよ」
「うむ。だがそのようにして以来、生徒もよくいうことをきくようになったわけだしね」
「けど、ねえ……」
「君はしらないんだよ。子供はああでもしないと言うことをまったく訊かないんだから。大人を舐めているんだからね」
「そうかしら」
「ともかく、結果が全てなんだよ」かつては、上司によく言われた台詞だった。「だいいち、僕だって、すきで生徒の顔や頭を叩いているわけじゃないんだ」
「だったら、手が勝手に動いているとでもいうの?」
「手が勝手に動くのは、君とこうしているときだけさ」
「いやだわ、シーツが勝手に湿っていくんだから」
右手がいうことを利かなくなっていく。まるで、手が独りでに人格を持とうとしているかのように――。
ある日、
「何をそんなに怯えているんだい、公子」
「あなた、その右手」
「……ナンでもない。見なかったことにしておきなさい」
――。
「せんせい、お手手を怪我しちゃったのぉ?」
「いま、わたしにちかよるんじゃない……」
――。
「君、君、何をしているんだね。川原で岩などを殴りつけたりなどして。手が血まみれじゃないか」
「おまわりさん、しばらく放っておいてくださいな。べつに、誰かを傷つけているわけではないんですから……。少しすれば、気が収まりますから」
――。
「先生のお手手、毛むくじゃら。そんな長い爪で、算盤なんてできっこないんだ」
「ヨウカイだ、ヨウカイだ」
「そんな爪で叩かれたら、僕らは死んでしまうんだ」
「妖怪だゞ」
もう、気が狂ってしまいそうだ…………。
見るに見かねたカマイタチが彼をいよいよ斬りつけたのは、その夜の事だった。人の中に巣食う妖怪は、のちに鼬だけでなく生けとし生きるもの全ての存在を脅かしかねない。
カマイタチに斬りつけられた人間は、次の満月の日まで生死の間をさまよい続ける。そのミニ宿した妖怪が息絶えるのが先か、あるいは宿主の命が尽き果てるのが先か。それは鎌鼬にもわからないし関心を持ち合わせていない。ただ、人の中に救う妖怪を人と同時に斬りつけるのみである。
三日三晩制止の間を彷徨ったあと、彼は病院のベッドの上で目を覚ました。
「驚いたわ、突然手を斬りつけて、そのまま倒れ込んだんですから」
「僕の顔は、鼠か鼬のような姿になっていやしないかい……?」
「へ?」
「あれは幻覚だったのか。確かに見たはずなんだが……」
「あなたのままよ」
「そうか。ところで、算盤しか脳のないこの僕だ。だけど右手がこうなったのではもう算盤すらはじくことが出来ない。もう、僕のことなど捨てるなりナンなり、どうにでもしておくれ。僕は一向に気にしたりはしないから」
「そうね、だけどその前にもう一度何か挑戦してみたらどう? あたしもその結果を見てから決めることにするわ。だって、手のない人なんて、この世にはたくさんいるんだもの。それで生きていられるんだから、人間って、きっともっと強い生き物なのにちがいないわよ」